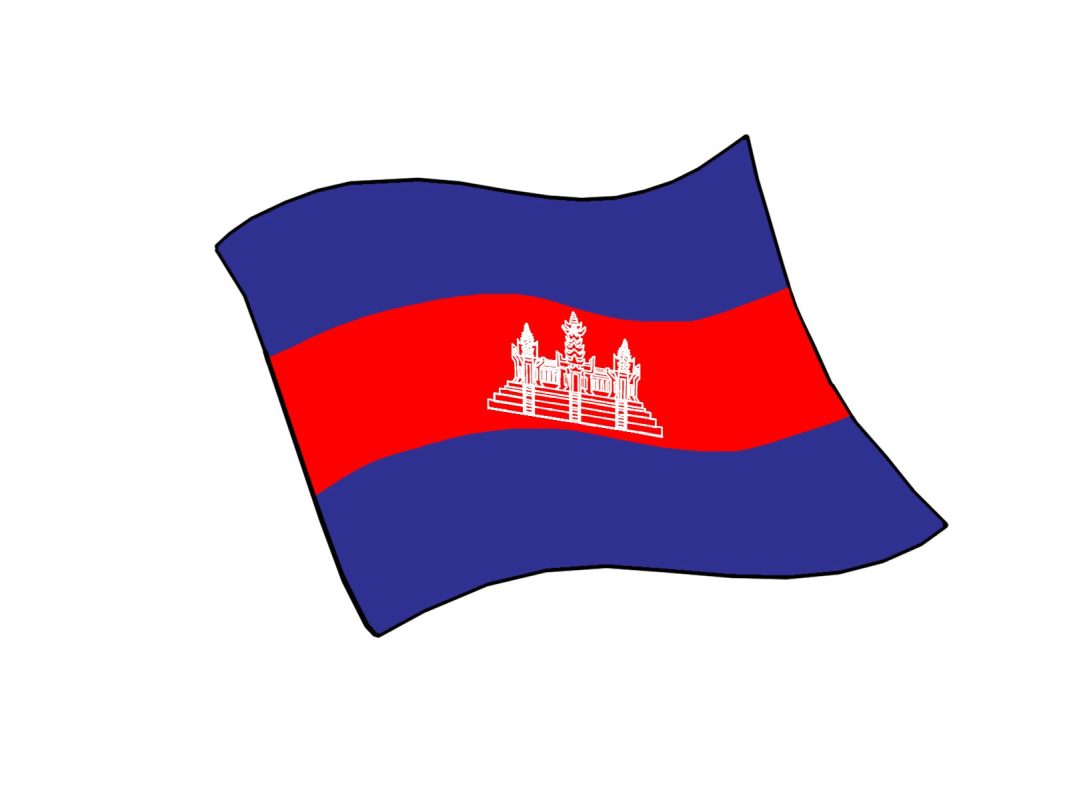在留資格「特定技能」を利用して人手不足解消が目指せます。
本記事では「カンボジア人を特定技能の在留資格で採用したい」と考えている企業さまのため、特定技能のカンボジア人の現状や確認しておきたいポイントなどを紹介します。
この記事を読むことによっておさえておくべき基礎知識や特定技能のカンボジア人を受け入れる際の流れ、費用などがわかるので、ぜひご覧ください。
カンボジア人の特徴
カンボジア人は温厚で素直、家族や共同体を大切にしています。
また友好的でオープンな性格であることから、仕事でも協調性を持って仲間と助け合うことができます。
年上の人を敬い、上下関係を重んじる文化も特徴です。
最近では英語を話すカンボジア人も増えてきており、日本での外国人観光客への対応にも貢献してくれるでしょう。
【カンボジアの基礎情報】
|
人口
|
1,720万人※2022年国連人口基金参照 |
|
平均年齢
|
26.5歳 |
|
言語
|
クメール語 |
|
宗教
|
仏教(一部少数民族はイスラム教) |
特定技能のカンボジア人の現状
現在、日本ではどの程度の数のカンボジア人が特定技能の在留資格で働いているのでしょうか。
出入国在留管理庁が発表している令和5年6月末次点のデータによると、特定技能1号の資格で働くカンボジア人の総数は3,659人です。
国籍・別にみるとベトナムが最も多く、カンボジアは上から6番目の数字となります。
職業の分野別にみてみると、カンボジア人が最も多く働いているのは、農業分野で1,889人となります。
続いて飲料食品製造業分野が757人、建設分野が502人と続きます。
分野別に見て最も少ないのは航空分野と漁業分野でそれぞれ0人、次が宿泊分野で2人でした。
カンボジア人全体で見てみると、農業分野が約半数を占めています。これは、その他の国と比較してみても高い割合です。
例えば、特定技能1号の在留資格で働いている方が最も多いベトナム人は農業分野の割合が8%程度でした。
参考:(PDF)出入国在留管理庁:特定技能在留外国人数[PDF]
二国間協定とは
日本とカンボジア間では「二国間協定」と呼ばれるものが結ばれています。
これは、円滑・適性に特定技能の制度を運用することを目的として作られた制度です。
両国に設置される連絡窓口や認定機関に関すること、必要な情報の公表などが定められています。
また、二国間協定によってカンボジアからは適切な選定を受け、必要な指導を受けたカンボジア人のみが日本に送り出されることになっています。
送り出し機関とは
二国間協定に基づき、カンボジアから特定技能の在留資格でカンボジア人を採用する場合、カンボジア国内で認定されている送り出し機関を介す形で送り出してもらわなければなりません。
送り出し機関のサポート内容と費用を紹介します。
送り出し機関のサポート内容
送り出し機関では、主に以下3つのサポートを行っています。
【主なサポート】
|
現地において日本で働きたい人材を募集します。
希望者が見つかった場合、そのまま日本で紹介するのではなく、送り出すための準備を行うのも送り出し機関の役割です。
日本語研修のほか、日本語テスト、技能試験合格における指導などを行います。
日本で生活するにあたり、困らないように文化やマナー、道徳的ルールなどを教育した上で日本へ人材を紹介する形です。
送り出し機関への費用支払いが必要
送り出し機関を利用するのには20〜60万円程度の費用がかかりますが、この費用は特定技能外国人本人が教育費などの名目で支払います。
ただ、企業によっては本人に代わって費用を負担しているところもあります。
現地から特定技能のカンボジア人を受け入れる際の流れ

カンボジアの現地から特定技能による在留資格で採用する場合の流れは以下の通りです。
【全体の流れ】
|
それぞれ解説します。
現地認定の送り出し機関と提携
先に現地認定送り出し機関と提携しましょう。
選択する機関によって評判などが異なるので、よく比較したうえで検討する必要があります。これまでの実績なども確認しておきたいところです。
雇用契約
受入機関となる企業は、送り出し機関を通して人材の紹介を受け、雇用契約を締結します。
カンボジアから認定を受けていない送り出し機関から紹介を受けることは認められません。
なお、認定送出機関のリストは日本の法務省のホームページで公開されています。
登録証明書の発行
特定技能外国人が認定の送り出し機関を通じてカンボジア労働職業訓練省に対して登録証明書の発行を申請します。
発行にかかる時間は2~3営業日です。
在留資格の取得申請・ビザの発給申請
受け入れ機関は特定技能外国人から登録証明書を受け取り、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。
その後、交付された在留資格認定証明書を特定技能外国人に送付し、本人はそれを在カンボジア日本国大使館に提示してビザを申請します。
出国前オリエンテーション
特定技能外国人はカンボジア側で出国前オリエンテーションを受講します。
その後、所定の手続きを行い特定技能の在留資格が付与される流れです。
日本在住である特定技能のカンボジア人を受け入れる際の流れ
すでに何らかの在留資格を持って日本で生活しているカンボジア人を特定技能で受け入れる方法もあります。
全体の流れは以下の通りです。
【流れ】
|
それぞれについて紹介します。
人材募集
求人情報を出して希望者を探します。
国内在住の方を採用する場合、認定送り出し機関を通して紹介を受けることも可能ではありますが、送り出し機関の利用は必須ではありません。
雇用契約締結
認定送り出し機関から紹介を受けるか、直接採用活動を行い、雇用契約を締結します。
登録証明書の発行
就労を希望する本人が登録証明書を申請します。
カンボジア国籍の方が特定技能外国人として就労する場合、日本在住であっても認定送出機関を通じてカンボジア労働職業訓練省に対して登録証明書の発行依頼が必要です。
在留資格の変更許可申請
現在対象となっている在留資格を、特定技能外国人として就労するための資格に変更する必要があります。
就労を希望する本人が地方出入国在留管理官署に対して事前に発行申請をしていた登録証明書を添付し、在留資格変更の手続きを行います。
関連記事:特定技能外国人を採用する際の流れとかかる費用を解説
採用にかかる費用

現地から採用する際、どの程度の費用がかかるのか確認しておきましょう。
費用例は以下の通りです。
|
費用項目 |
費用相場 |
|
送り出し機関への手数料 |
20〜60万円 |
|
人材紹介の手数料 |
30~60万円 |
|
渡航費用 |
実費 |
|
在留資格申請費用 |
10〜20万円 |
|
住居準備費用 |
初期費用全般(住居の家賃によって異なる) |
|
事前ガイダンス等の費用 |
1.5〜4万円 |
|
支援委託費用 |
2〜4万円/月 |
|
在留資格更新費用 |
4〜10万円 |
現地から採用する場合は、特定技能外国人を日本へ送る役割を持った送り出し機関を通さなければなりません。
そのため、送り出し機関への手数料が発生します。
渡航費用については、必ずしも受け入れ企業が支払う必要はありません。
ですが、多くの企業が企業負担としていることから、本人に負担させる場合は採用活動が不利に働く恐れがあります。
できれば企業負担で検討した方が良いでしょう。
それから、カンボジアにはデポジットと呼ばれる敷金と同様の制度がありますが、礼金など日本独自の風習はわかりにくく、個人が賃貸契約するには難しい面があります。
そのため、特に現地から採用する場合は受け入れ企業が住宅を借りるための契約をするのが一般的です。
この場合、契約によって発生する費用を本人に負担させることはできないので注意しましょう。
本人が契約をする場合、その費用を本人負担とすることは不可能ではありません。ですが、やはりこちらのケースでは採用活動において不利になってしまう可能性も考えられます。
注意点として、送り出し機関の中には渡航や住居の準備にかかる費用を企業負担と定めているところもあります。
事前に確認が必要です。
国内在住の方を採用する場合は、送り出し機関への手数料や渡航費用はかかりませんが、住居の準備にかかる費用は企業負担となることがあります。
関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント
各ポイントを確認した上で採用活動を
いかがだったでしょうか。
在留資格特定技能でカンボジア人を採用するにあたり、おさえておきたいポイントを紹介しました。
事前に確認しておきたい基礎知識や、全体の流れなどをご理解いただけたかと思います。
特に現地からの採用は自社だけでは対応が難しいことがあるので、専門家に任せてみてはいかがでしょうか。
「スタッフ満足」では、外国人の採用をサポートしています。
外国人教育支援プロジェクトなども行っているので、カンボジア人の採用で困っていることがある方はぜひご相談ください。